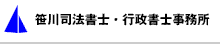相 続 人

相続人になれる人は民法で定められています
⇒法定相続人
その定められた範囲の人だけが相続人となります
法定相続人
・配偶者
・直系卑属
子供=実子、養子、非摘出子、胎児、孫 、ひ孫
子が死亡または相続権を失ったときに孫が相続人になります
孫が死亡または相続権を失ったときにひ孫が相続人になります
※非摘出子…法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子
認知されると相続できます 。
※連れ子…連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が死亡した場合、連れ子は相続権はありません
相続できるようにするためには、
再婚相手と生前に養子縁組を結んでいなければいけません。
・直系尊属
父と母、あるいは祖父母
父・母が死亡または相続権を失ったときに祖父母が相続人になります
・兄弟姉妹 あるいは、甥・姪
兄弟姉妹が死亡または相続権を失ったときに甥・姪が相続人になります
|
例えば…
ケース1 亡くなられた方に妻と子供がいる場合 →妻と子供だけが相続人になります
ケース2 亡くなられた方の妻も亡くなっており、子供だけがいる場合 →子供の全員が相続人になります
ケース3 亡くなられた方に子はおらず、妻だけがいる場合 →妻と、亡くなられた方の父・母、 あるいは祖父母が相続人になります
ケース4 亡くなられた方の妻はいるが、 子はおらず、父・母、祖父母もいない場合 →妻と、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります
→亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります
その他具体的なケースについては、ご相談ください |
|
相続人を調べる方法
1.被相続人の戸籍謄本をとる 被相続人の本籍地の市町村役場で、申請します。
2.被相続人の出生まで遡って戸籍をとる
戸籍には、以前にどこの戸籍から入籍したかが記されており その記録から、前の戸籍を調べていきます。 ・除籍謄本 戸籍に記載されている人が婚姻や死亡等により抹消され、 全員いなくなった戸籍 または、他の市区町村へ本籍を移した場合の、元の本籍地の戸籍
・改製原戸籍 現在の戸籍ではなく、現在の戸籍に書き換えられる前の元の戸籍
が必要になる場合もあります。
3.法定相続人を確定する 子どもが、被相続人の戸籍から出ているときは、 その子どもの戸籍も必要になります。
戸籍を集めていく作業は、とても労力のいる作業になることも! 後になって、知らなかった相続人が現れたりすれば、 また大変な手続きが必要になります。 相続人を正確に把握するためにも、複雑な時、ご不明な時には、
専門家に依頼されることをお勧めします。
|

私は相続人になれますか?
非摘出子
※非摘出子…法律上、婚姻関係にない夫婦から産まれた子
母親と非嫡出子は出生により母子関係が生じますが、
父親と非嫡出子は、父親が認知して、初めて父子関係が生じます。
父親の相続人となるのは、認知した非摘出子だけです。
養子
養子は相続人となります
また、実の父母とも親子でなくなるわけではないので、
養子は、養父母・実親の両方の相続人になります。
特別養子は実親との親族関係が切断され、養父母の実子となりますので
養父母の相続人となり、実親の相続人にはなりません。
※特別養子…子供と実親との親族関係が終了し、法律上は他人となる
離婚した元妻と子
離婚した元妻は相続人にはなりません。
子どもは、離婚して父母のどちらが引き取ったかに関わらず、
摘出子として相続人となります。
※摘出子…法律上、婚姻関係にある夫婦から産まれた子
再婚した妻とその連れ子
再婚した妻は、相続人になります。
その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていれば相続人になります。
養子縁組していなければ、親族関係にはならず、相続人にはなりません。
内縁の夫・妻
法律上の婚姻関係にある配偶者が相続人となります。
よって、内縁関係の夫・妻は相続人になりません。
胎児
相続開始の時、まだ産まれていない胎児は、
生まれたものとみなされ、相続人となります。
内縁関係の場合
|
内縁関係(事実婚)とは 婚姻届を出していないため、法律上の婚姻とは認められないが 婚姻の意思を持ちながら、共同生活している関係 のことをいいます
内縁関係で、生計をひとつにしている場合は、配偶者とみなされ 年金など、様々な権利が認められるようになってきました ・同居義務 ・扶養義務 ・貞操義務 なども、法律婚と同様に課せられます
しかし、相続する権利は認められていません!!
★内縁関係の相手に遺産をのこすには、遺言を書いておく必要がります |
子どもがいないお嫁さんの場合
|
子がいない妻の場合、夫が義父母より先に死亡していると、 義父母の遺産は相続できません!!
★むすこと共に家業を守るためによく頑張ってくれたお嫁さんへ… ★むすこが亡くなったあとも、よく面倒をみてくれたお嫁さんへ… 感謝の気持ちを、相続という形で残すには 遺言書を書いておく必要があります |
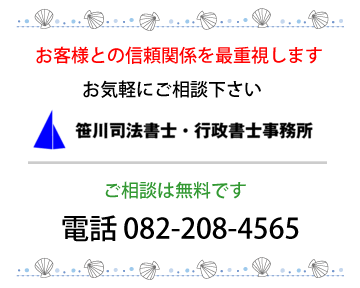
 佐伯区・西区・廿日市の相続ならお任せください
相続対策相談所
広島の笹川司法書士・行政書士事務所
佐伯区・西区・廿日市の相続ならお任せください
相続対策相談所
広島の笹川司法書士・行政書士事務所